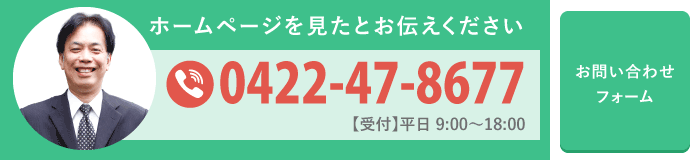このページの目次
2024年の改悪
2023年の確定申告までは所得税を総合課税、住民税を申告不要とすることで源泉徴収された所得税の還付請求をしつつ、住民税、国民健康保険料の負担増を抑えることができました。
皆さんもご存じのとおりそれが改悪されて、2024年からは所得税を総合課税とするなら住民税も総合課税というように同一の課税方式によることとなり、住民税、国民健康保険料の負担増となって総合課税、分離課税(申告不要)のどちらを選択した方がよいのかを判断しなければならなくなりました。
もちろん、所得が低く所得税も住民税も非課税となる方は総合課税を選択することになるかと思いますが、その場合でも国民健康保険料の負担は増加しますので、改悪であることに変わりはありません。
誤解を招くSNS上の配当控除の解説
よく見られるのが源泉徴収の税率は20.315%(所得税15.315%・住民税5%)だから、実質的な税率がそれよりも低くなる課税所得金額695万円以下であれば総合課税を選択した方が得になるというものです。100%間違っているとは言いませんが、配当控除は税額控除なわけですから、実質的な税率が当てはまるのは配当所得しかない人です。
個人事業主であれば、配当所得以外にも事業所得、不動産所得等の所得がある場合の方が多いと思いますので、配当所得以外の所得については課税所得金額に応じた所得税率、住民税は一律10%で課税されるのです。ですから、一律に実質税率を持ち出して、ボーダーラインを判定する説明には違和感を覚えます。
住民税の試算
前述したように配当所得以外の所得には10%課税されますので、確定申告した方が良いのか否かについては住民税自動計算サイト等を使って試算してみることをお勧めします。
配当控除2.8%、源泉徴収された配当割額控除などは分かりやすいと思いますが、調整控除というものもあります。詳しい説明は割愛しますが、課税所得金額が200万円以下の場合には控除額がある程度の金額となる場合もあるので、控除額として無視することはできません。
自動計算ツールは住民税非課税の判定に対応してないこともあるようですので、お住まいの市町村のホームページ等で確認することも重要となります。また、2024年には定額減税もありますので、引ききれない個人事業主、同年起業された方等はそれも考慮したほうがよいでしょう。
国民健康保険料の試算
個人事業主が配当金を確定申告するうえで、最も注意しなければならないのは国民健康保険料の負担増です。
ちなみに、東京都武蔵野市の令和6年度所得割率の基礎課税額については、前年度から0.52%増の5.62%となっています。同市のホームページ上には税額試算シート(Excelファイル)が掲載されており、世帯員区分や所得額等を入力することによって概算額を試算することができます。
他の市町村においては、同様のことが可能かはわかりませんが、全国の市町村に対応したサイトもあるようですので、是非とも利用しておきたいところです。
最後に
税負担が増えていくのは仕方のないことだと思いますので、受け入れるしかないです。それにしても、個人事業主が負担しなければならない国民健康保険料は高いと感じています。扶養家族が増えるほどそれを痛感することになるでしょう。
節税対策として、マイクロ法人を設立する方法もあるようですが、子供が2人以上いる世帯なら考えてみても良いと思います。ただ、そのような方法が一般的になってしまいますと、できなくなるような法整備がされる気がします。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。