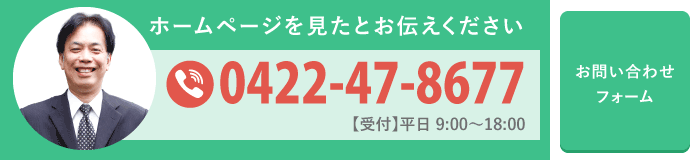このページの目次
管轄とは
特定の事件についてどの裁判所が裁判権を行使するか、言い換えれば、具体的事件を裁判によって処理するかに関する定めのことを管轄といいます。
管轄の種類
管轄については民事訴訟法等に規定されていますが、発生事由によって、法律の規定により発生する法定管轄、直近の上級裁判所の指定により発生する指定管轄、当事者の合意により発生する合意・応訴管轄に分類されます。
また、裁判所の分担を決める基準による分類として、どの種類の手続をどの種の裁判所の役割にするかによる定めである職分管轄があります。簡易裁判所が第一審裁判所となった場合に、どの裁判所に上訴できるかを定めた審級管轄や判決手続をする受訴裁判所と執行手続をする執行裁判所の区別が職分管轄の一種となります。
加えて、第一審裁判所を簡易裁判所と地方裁判所のいずれにするかに関する定めである事物管轄及び全国の同種類の第一審裁判所の間での事件の分担に関する定めである土地管轄に分類されます。
事物管轄
簡易裁判所は訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない請求につき管轄権を有し、地方裁判所はそれ以外の請求につき管轄権を有するのを原則としますが、不動産に関する訴訟については、訴額が140万円を超えない場合であっても、簡易裁判所及び地方裁判所の双方が管轄権を有するものとされています。
訴額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなされますので、地方裁判所の管轄とされます。
土地管轄
普通裁判籍
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するとされています。これが原則となりますが、自然人を被告とする場合については住所または居所、法人を被告とする場合については事務所または営業所とされます。
特別裁判籍
普通裁判籍は事件の種類に関係なく常に認められる裁判籍ですが、特定の種類の事件について認められる特別裁判籍があります。特別裁判籍は、他の事件と無関係に認められる独立裁判籍と他の事件との関連から生じる関連裁判籍に分類されます。以下に、独立裁判籍のうち主要なものを掲げます。
- 義務履行地
財産権上の訴えについては、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができます。義務履行地は当事者の特約があればそれによって定まりますが、ない場合には民法等の規定によります。
義務履行地について、原則として債権者の現在の住所または営業所(持参債務)とされています。要するに、原告である債権者は被告の住所地を管轄する裁判所(普通裁判籍)以外にも義務履行地である原告の住所地を管轄する裁判所へ提訴することができるのです。 - 財産所在地
日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴えは、被告の財産の所在地を管轄する裁判所に提起することができます。 - 事務所・営業所の所在地
事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するものについては、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。 - 不法行為地
不法行為に関する訴えについては、不法行為があった地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。不法行為地には、不法行為が行われた地と損害が発生した地のどちらも含まれます。 - 不動産所在地
不動産に関する訴えについては、その不動産の所在地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。 - 相続に関するもの
相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え等は、被相続人の死亡時の住所又は居所地を管轄する裁判所に訴えを提起することができます。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。