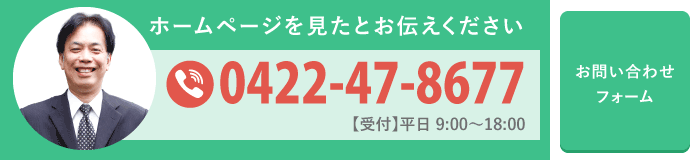このページの目次
2問70点から140点満点に
令和5年12月4日、法務省から令和6年度以降に実施する司法書士試験筆記試験午後の部の記述式問題の配点を変更することが公表されました。【変更内容】として、「2問で70点満点」から「2問で140点満点」に変更します、と記載されています。
実際に法務省のウェブページを見にいったのですが、理由の記載等もなく、あまりに簡潔な内容のために拍子抜けしてしまいました。
変更によって、択一式210点(60%)・記述式140点(40%)の配点となり、記述式の配点割合は上昇することになりましたが、択一式の配点割合を超えるまでには至りませんでした。
理由は?
1つ目の理由として、試験時間内に解き終えることができないほどに問題の分量が増えたことが考えられるでしょう。そのことによって、0.5点刻みの配点をしなければならなくなりますので、それを解消するためかもしれません。
2つ目は、択一問題得意な法律知識先行型の者より、実務能力に長けている者を司法書士として選抜したいのではないかということです。
対策は?
あくまでも私見ですが、特別な対策は不要で今まで通りの勉強方法で良いのではないかと思います。記述式の配点割合は増えましたが、依然として択一式の配点の方が多いので、択一で逃げ切り点を確保して、記述式の基準点を死守するのが良いのではないでしょうか。ただ、択一の基準点を下げて記述の被採点者数を増やすようなことがあるのなら、他の対策も考えられるかもしれません。
司法書士試験の受験者数は年々減少していますが、被採点者数は約2,000人となっており、毎年これが維持されています。令和6年度以降も踏襲されると予想します。
ところで、令和3年度から司法書士試験の出願者数が増加しています。その後も増加が続き、令和6年度の出願者数は16,837人、前年度より4.4%増加で、令和に入ってから最も多くなっています。
相対評価試験
司法書士試験は、上から順番に取っていく相対評価試験です。この点が、6割取れば合格する行政書士試験と異なります。また、3つの基準点の設定によって不得意科目があると合格できない試験であることも特徴です。それ故、特別な対策は不要ではないかと考える訳です。
記述得意な人が挽回可能になるという見方もあるようですが、そもそも何々が得意とか言っている時点で上位5%の争いの場に立つことさえ困難なことだと思います。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。