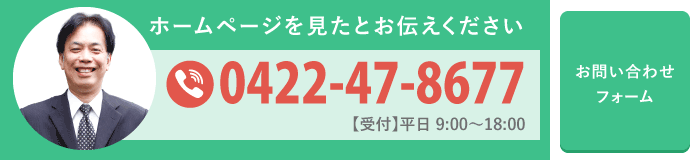このページの目次
農地の所有権移転の効力発生日
農地の所有権を移転するには、売買契約等の締結及び農地法所定の許可到達の両方が必要です。通常、両者の日付は一致しないことが多いので、契約締結日と許可到達日のうち後の日付が所有権移転の効力発生日となります。
以上のことから、契約締結後、許可が到達する前に当事者が死亡した場合に、相続登記の要否が問題となります。
許可到達前の売主死亡
売主について相続による所有権移転登記を申請した後、買主への売買による所有権移転登記を申請します。
相続登記を省略することはできません。許可到達前に売主が死亡していますので、農地の所有権は一旦売主の相続人に移転します。不動産登記制度における物権変動の過程を忠実に公示すべきであるという原則の存在がその理由です。
令和7年度司法書士試験
今年の試験の不動産登記記述式問題で上記の論点が出題されました。AB共有の甲土地に農地法第3条の許可を停止条件とする「条件付共有者全員持分全部移転仮登記」がされ、その仮登記の本登記を申請するにあたり、農地法所定の許可到達前にBが死亡した際の相続登記の要否を問う問題です。
法務省は模範解答例を公表しませんので、予備校のものを参照すると相続登記は省略しているようです。その根拠として、先例の存在を掲げています。Bの相続登記を申請しても、仮登記の本登記申請によってその登記が職権抹消されてしまうから省略可能という内容のものです。
あくまでも、申請人の負担を考慮して便宜的に省略を認めている趣旨だと考えます。登録免許税の負担もありますし、もっとも、農地なので租税特別措置法によって非課税になるとは思いますが、申請件数が増えるのは負担となります。
試験問題では「答案作成に当たっての注意事項」により、相続登記不要というのが出題者の意図ではないかと捉えられているようです。
では、実務上相続登記を申請すると却下されてしまうのかというと、そんなことはありません。寧ろ、物権変動の過程を忠実に公示すべきであるという要請に応えるべく相続登記は省略できないという見解を有する人達もいらっしゃるようです。
許可到達後の売主死亡
売主の相続人全員と買主の共同申請により所有権移転登記を申請します。
この場合、許可到達によって農地の所有権は買主に移転しますので、売主の相続人に所有権が帰属する余地はありません。
許可到達前の買主死亡
農地法第3条の許可申請は売主及び買主が共同で行います。実務上は、行政書士が双方の代理人として申請することが圧倒的に多いです。言うまでもなく、許可の時点で買主が亡くなっていますので、死者に対してその効力が生じることはありません。
したがって、売買による所有権移転登記の申請はできないことになります。
許可到達後の買主死亡
売主と買主の相続人の共同申請により、買主を登記名義人とする所有権移転登記を申請します。
買主は生前に許可を得ていますので、その時点で農地の所有権を取得しているからです。

司法書士の藤山晋三です。大阪府吹田市で生まれ育ち、現在は東京・三鷹市で司法書士事務所を開業しています。人生の大半を過ごした三鷹で、相続や借金問題など、個人のお客様の無料相談に対応しています。
「誰にも相談できずに困っていたが、本当にお世話になりました」といったお言葉をいただくこともあり、迅速な対応とお客様の不安を和らげることを心掛けています。趣味はドライブと温泉旅行で、娘と一緒に車の話をするのが楽しみです。甘いものが好きで、飲んだ後の締めはラーメンではなくデザート派です。
三鷹市をはじめ、東京近郊で相続や借金問題でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。